前回に引き続き、ギリシア哲学者たちを紹介していきます。
今回はギリシア哲学者といえばの方々、ソクラテス、プラトン、アリストテレスです。
そもそもソクラテスは何を説いたのか、その弟子たちは何をしたのか。
- ソクラテスが考える哲学
- プラトン
- アリストテレス
ソクラテスが考える哲学
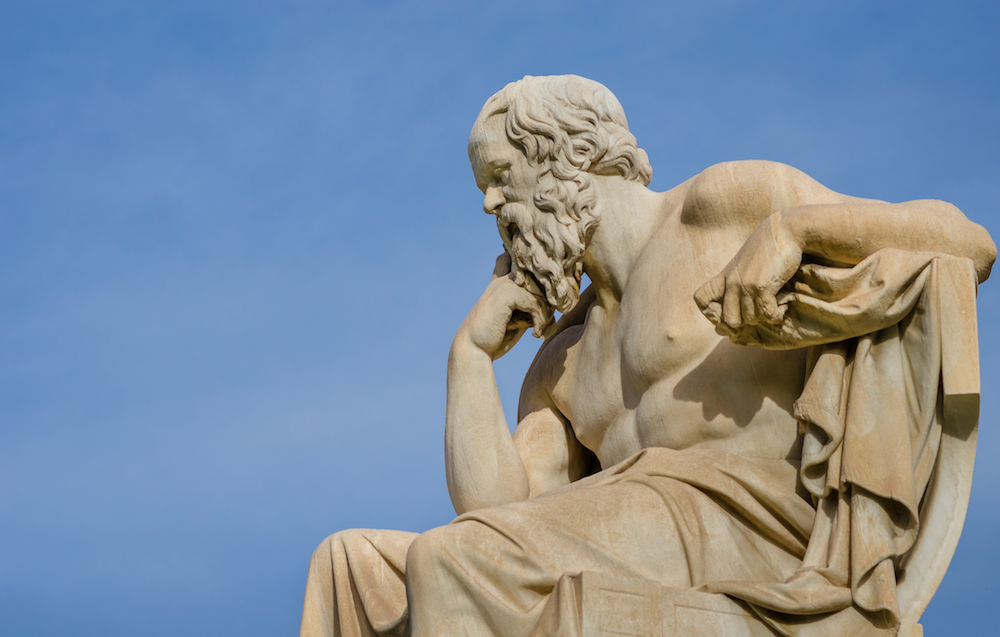
当時のアテネでは多くの学問が流行っており、人を議論で打ち負かす弁論術も教えられていました。
その弁論術はソフィストと呼ばれる人たちが広場(アゴラ)で青年たちから金を受け取り教えていました。
そんな中で「学問というのは他人を理屈で打ち負かすためにある」というソフィストもいました。
そのようなソフィストに反論したのがソクラテスです。
彼は「真理の存在を見出し、真理に従ってこそいい生き方が出来るのだ。」
と主張し、対話法(ソクラテス的問答法)を用いて、人々と対話を重ね、相手の考えを深掘りし、
矛盾を指摘することで真理を見出そうとしました。
有名なことは「無知の知」です。それを悟ったのはデルフォイの信託からだと言われています。
ある日、ソクラテスの友人がデルフォイの神託に訪れ、「ソクラテスより賢い人がいるか」と尋ねたところ、神託は「いない」と答えました。
これに驚いたソクラテスは、本当か確認したかったため賢者といわれる人たちに聞いて回りました。
ところが賢者たちは「自分が一番賢いのだ」といい他人の話を聞きません。
そこで彼は自分の無知を自覚している者が最も賢いのだと悟り、「無知の知」という考えを提唱しました。
彼はユーモアにも富んでいたそうです。こんなエピソードがあります。
ソクラテスには妻がいました。名前はクセンティッペ。
彼女は非常に気性の荒い女性として知られていました。
ある日、彼女がソクラテスに激しく文句を言った後、怒りに任せて彼の上に水をぶっかけました。
ソクラテスは冷静に「雷(妻の激怒)の後に必ず雨が降るものだ」と答えました。
こんな妻なら別れればいいのにと周りの人に言われると、
「結婚はするべきだ。良妻なら幸せになれるし、悪妻なら哲学者になれる。」とも言ったそうです。
そんなソクラテスですが最後はソフィストたちに訴えられます。
紀元前399年、そのアテナイの裁判で「若者を腐敗させた」と「神々を冒涜した」という罪で有罪判決を受けました。
彼は死刑を宣告され、毒杯(ヘムロック、毒ニンジン)を飲むことが命じられます。
その判決の抗うことなくソクラテスは毒杯を飲むまで弟子たちと対話を続けていきます。
そして彼は毒杯を受け取ったとき、弟子たちに最後の言葉を残しました。
それは、「クリトン、アスクレピオスに鶏を一羽捧げなければならない。忘れないでくれ。」というものでした。
この言葉には様々な解釈がありますが、一つの解釈として、ソクラテスが死を病からの解放と捉えていたことが考えられています。
最後まで信念に従い、法律と国民の義務を尊重し死にました。
プラトン
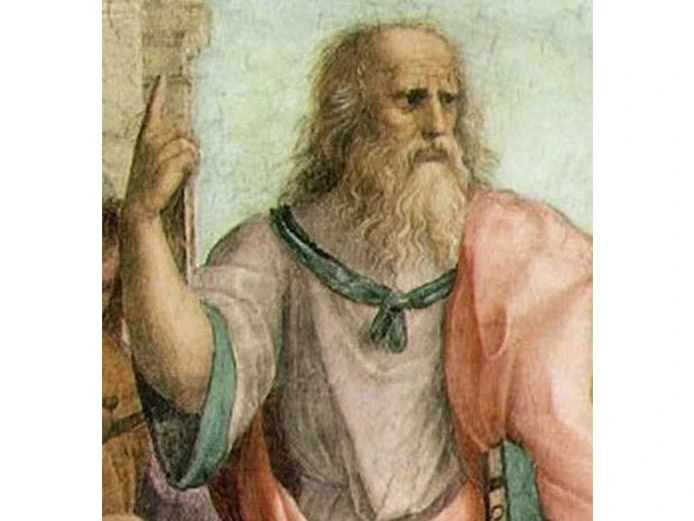
そんなソクラテスの弟子の一人がプラトンです。
彼は「ソクラテスの弁明」や「国家」などソクラテスの思想を題材とする本を書きました。
プラトンは「現実世界の背後には理想的で永遠不変の「イデア」(Forms)という抽象的な実体が存在するとするものです」といい、
物事の本質や完全さは心の中で見ることが出来るという「イデア論」を主張しました。
プラトンは紀元前387年にアテネにアカデメイアという学問の場を設立し、
そこでソクラテスのように弟子との対話を通じて哲学を深めていきました。
プラトンにも逸話がいくつかあり、例えば、彼が「人間とは羽のない二足歩行の動物である」と定義したときのことです。
この定義を聞いた犬儒派の哲学者ディオゲネスは、鶏の羽をむしり取ってアカデメイアに持ち込み、「見よ、これがプラトンの人間だ!」と宣言しました。
この出来事を受けて、プラトンは定義に「平らな爪を持つ」という条件を付け加えたと言われています。(どんな意味なんやろ)
哲学者はやはり返しが凡人と違うんでしょうか。
アリストテレス
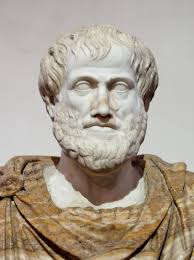
アリストテレスはプラトンの弟子であり、現実世界を学問の対象として研究することにより
本質に迫ろうとしました。少し姿勢がプラトンと違いますね。
アリストテレスはアレキサンドロス大王の教師として有名です。
アレキサンドロス大王の父フィリッポス2世から息子の教育を任されたアリストテレスは、
アレクサンドロスに哲学、倫理、科学、政治など多岐にわたる知識を伝授しました。
一説によると、アレクサンドロスが東方遠征で得た珍しい生物や植物のサンプルをアリストテレスに送ったことで、彼の生物学研究が大いに進展したとも言われています。
また彼が「歩きながら教える」スタイルを取っていたことをご存知でしょうか?
アリストテレスはアテネにリュケイオンという学園を設立し、弟子たちと共に園内を歩き回りながら対話と講義を行っていました。
このため、彼の学派は「ペリパトス派(逍遥学派)」と呼ばれ、「ペリパトス」はギリシャ語で「歩き回ること」を意味します。
歩きながら議論することで、自由な思考と深い洞察が得られると考えていたのでしょう。
やっていることはGoogleの会議と一緒ですね。歩いたほうがいいアイデアが生まれるんでしょうか。
著作には『ニコマコス倫理学』や『形而上学』などがあります。
むずいんで読むのは諦めました。
まとめ
以上師弟関係の三人をピックアップしました。
彼らの思想や哲学はのちの世界史の主人公であるアレキサンドロス大王や、
今に生きる我々にも大きな影響を与えています。
そしてそれぞれが自らの理想を持ち、信念に従いながら生きていきました。
かっこいい。



コメント